
盆栽は草木を扱う趣味として古くから日本で親しまれており、現代ではインテリアや芸術作品として扱われることもあります。
そんな盆栽について制作できる技術と共に、販売や指導ができる盆栽職人は、国外でも嗜まれる盆栽の需要に対応できる人物です。
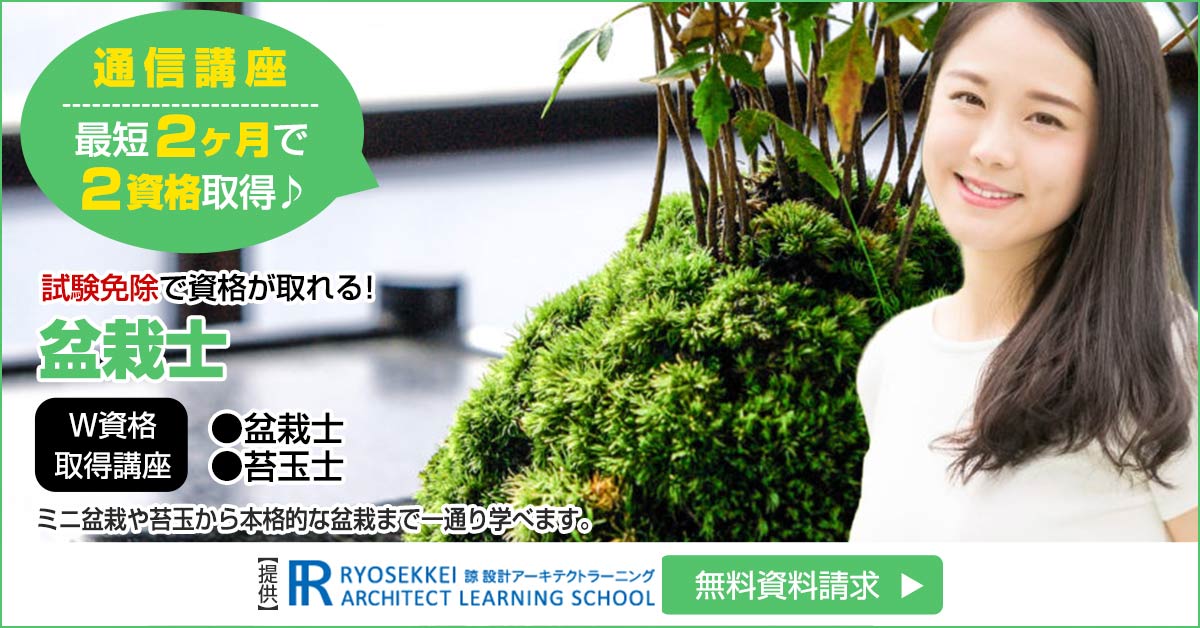

ここでは、盆栽職人について、仕事をする上での資格の必要性や取得に向けたおすすめの学習方法、職人として働く際の主な仕事内容などをまとめました。
盆栽とは、器物に植え付けた草木を枝切りや針金による固定などを施して、形を整えながら栽培された物です。
器物の中に自然にある樹木のような景観を作り出す目的で栽培されており、平安時代に中国から取り入れられた盆景が日本独自の趣味として変化したと言われています。

江戸時代辺りになると、他の園芸と合わせて盆栽も盛んに栽培されるようになり、現在は国外でも「BONSAI」の単語が通じるほど趣味や芸術の1種として広まりました。
盆栽は自由に作れるものですが、初心者の場合は盆栽の基盤を購入して、水やりや剪定(枝を切り狩りする)、日光を当てる調整などを行って自分の思い描いた形を作っていきます。
そんな盆栽に使用される草木・器物の知識や基盤から作れる技術があり、盆栽の作り方の指導をできる人物が盆栽職人です。
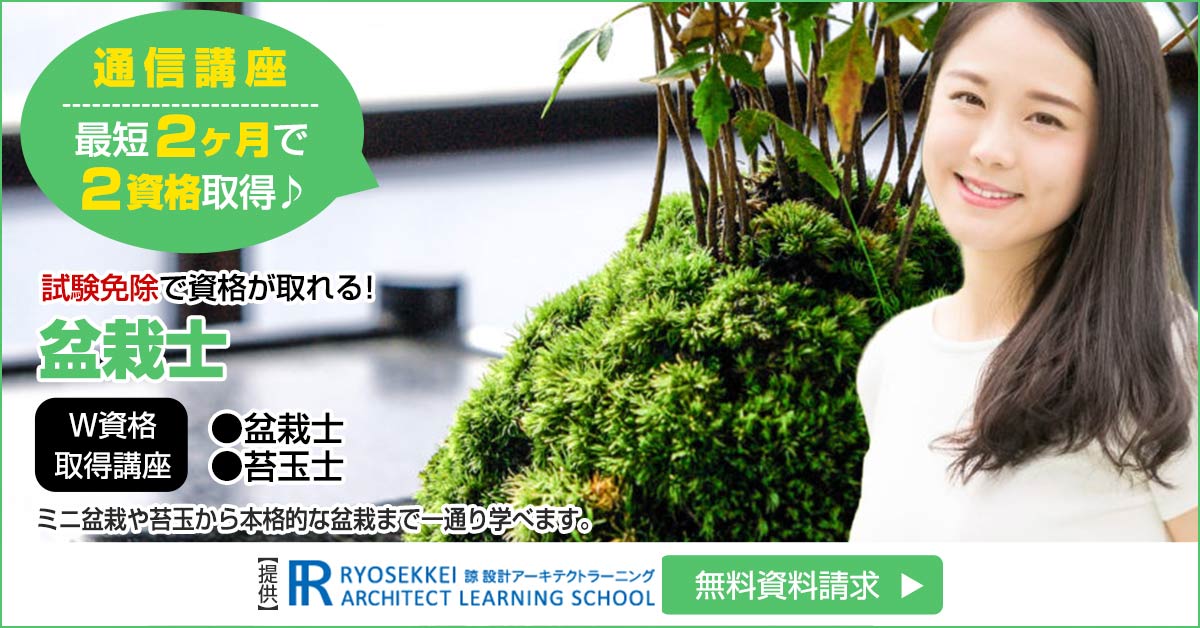

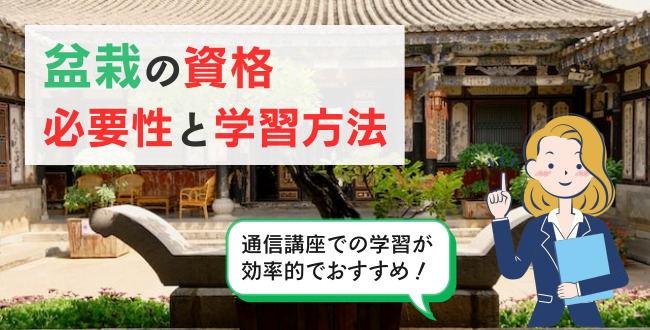
盆栽を基盤から作る場合、草木がある程度育つまで害虫や気温の変化から生じる病気などに対応しなければならないので、草木の種類ごとの管理方法などの幅広い知識が必要です。

そのため、盆栽に関わる知識や技術を明らかにできない状態で、盆栽職人として活動すると、商品や作品についてお客様から信頼されない可能性があります。
盆栽職人は資格が必須の職業ではありませんが、活動を始める場合は盆栽に関する知識や技術を示すための資格を所持しておいた方が良いでしょう。
盆栽の知識を学習できる方法としては、盆栽職人への弟子入りや盆栽の教室、通信講座が候補になります。
弟子入りは盆栽職人の元で活動を手伝いながら、自分で知識や技術を身に付けていくという方法ですが、そもそも弟子を取ってくれる盆栽職人が限られています。

また、盆栽職人として認められるまで5年以上かかると言われており、現在の仕事を完全に辞めた上で弟子になる必要があるため、万人向けの学習方法ではありません。
盆栽の教室は盆栽の基本的な部分を学習できる場ですが、趣味の範囲で指導する講座が多いので、専門的な部分は個人で学習する必要があります。
手軽に受講できるところはメリットですが、資格取得のための講座としては少し物足りない学習方法です。
通信講座は盆栽資格に対応した講座があるので、必要な知識や技術は通信講座だけで身に付けられます。
受講期間は半年から長くても1年程度で済み、教科書や動画などの教材で好きな時間に学習が進められます。
仕事を続けながら盆栽の知識を学習するなら通信講座の利用がおすすめです。
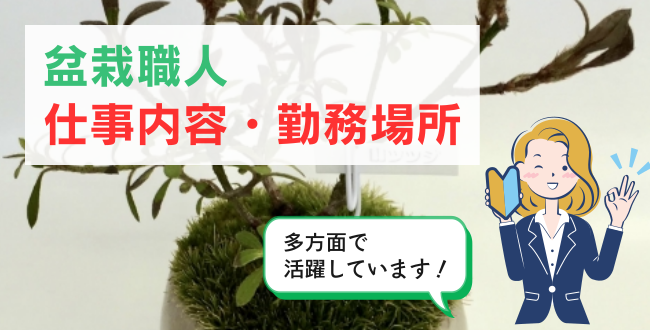
盆栽職人は販売や指導を仕事にしていきますが、1つの仕事に特化する人もいれば、盆栽に関わる仕事を総合的に行う人もいます。
そんな盆栽職人が活動する勤務場所や仕事内容を紹介します。

趣味として盆栽を嗜む人に向けた盆栽基盤の販売は、盆栽職人の主な仕事の1つです。
店舗を構えて勤務する働き方と、店舗は持たずにネット通販やオークションサイトで販売する働き方があり、ネットの場合は自宅を勤務場所にすることもあります。
草木や器物の選択、栽培中の管理などを行いながら基盤をある程度の段階まで育てて、店頭やネットで販売していきます。
盆栽の剪定や管理方法を学びたい人に向けた、盆栽教室も盆栽職人の主な仕事の1つです。
勤務場所は地域にあるカルチャースクールや自宅開業などの選択肢がありますが、草木を切る作業をしても問題ない場所であれば開講できるでしょう。

受講者の需要によっては基盤の作り方などを指導する場合もありますが、基本的には初心者向けの教室で基礎を中心に教えていきます。
また、近年では海外での盆栽の需要から、外国人が集まる日本語教室や海外の施設などに呼ばれて指導を依頼される場合もあります。

盆栽職人として実績を積み上げていくと、完成した状態の盆栽を作品・商品として販売する盆栽作家の道も開けてきます。
基盤と同じく店舗やネットで販売する他、名前が広まれば展示会などに出展する機会も出てくるでしょう。
インテリアやコレクションとして飾りたい人から依頼を受けるパターンもあり、その場合は海外から発注される可能性もあります。
盆栽職人の活動でやりがいになるのは、仕事の中で周りの刺激を受けながら自分の成長や変化を実感できるところです。
盆栽について学習すれば基盤の作り方や管理方法は同じ知識や技術が身に付きますが、作品・商品としての盆栽は制作者ごとに千差万別の仕上がりになります。
そのため、自分で盆栽を作ったり、盆栽の仕事に関わり続ける限り、常に新しい盆栽を目にしていきます。
その中で良い作品を見て刺激を貰えれば、自分の作品にも変化する場合もあり、そこから盆栽の中で新しい表現ができると成長する喜びを実感できるのです。

一方、盆栽職人の活動を続けていくためには、根気よく販売や制作を続ける必要があります。
盆栽の需要は一定数あるものの、職人として始めたばかりの時や名前が知られてない時には、思うように作品・商品が売れない可能性が出てきます。
特に完成した状態の盆栽を売り出すには、見合った実績が必要であるため、自作の盆栽だけで仕事をしていくにはある程度の年数は必要です。
それでも活動を継続していけば実力や認知度は確実に出てくるので、諦めずに基盤の販売や教室といった場所で活動を続けましょう。
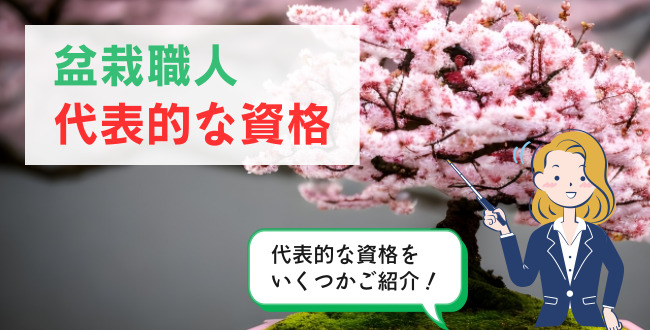
盆栽資格は様々な協会から発行されており、盆栽を含めた園芸全般の資格や盆栽に特化した資格など、資格ごとに内容は異なります。
盆栽資格の中でも代表的なものを紹介します。
盆栽士資格は、一般財団法人の日本園芸協会が発行している資格です。

協会では植物・園芸・ガーデニングの3つについての資格を取り扱っており、それぞれに協会が用意した専門通信講座が用意されています。
盆栽士資格では盆栽の基礎を総合的に身に付けたと証明して、実力を示せるようになります。
苔玉士資格は、日本インストラクター技術協会(JIA)が植物・フラワー・園芸の資格の1種として発行している資格です。

JIAでは特定の知識について指導力を証明できる資格を取り扱っており、取得後は専門知識のある指導者として活動できる人物になれます。
苔玉士資格では名前が苔玉になっていますが、盆栽も含めて季節に合わせた草木の選択や管理方法の知識や技術を明らかにできます。
盆栽士資格は、日本デザインプランナー協会(JDP)が趣味の資格の1種として発行している資格です。
JDPはデザイン系のスキルが仕事レベルであると証明できる資格を取り扱っており、空間デザインやファッション、ハンドメイドなどの資格があります。

盆栽士資格では盆栽の歴史から専門用語理解があり、盆栽の作り方や既存の商品の買い方など、幅広い知識を持っていると明らかにできる資格です。
なお、資格の名前は日本園芸協会と同じですが、発行元の協会や資格の内容は全く別の資格になります。
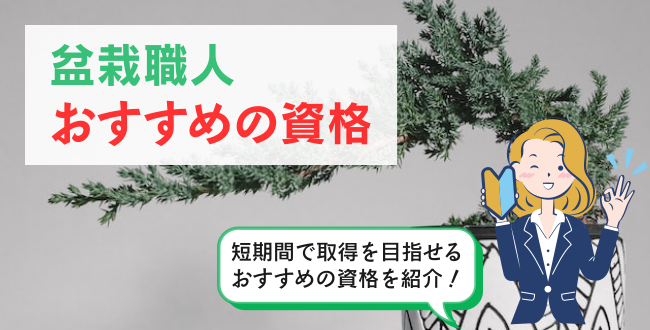
盆栽職人は仕事で資格が提示を求められる仕事ではありませんが、正しい知識や技術を身に付けていると明らかにできなければ、活動していく上で信頼を得るのが難しい職業です。

販売や指導の場で盆栽の代表的な資格を提示できれば、協会が認めた知識や技術を示せるので、1種類でも取得しておいた方が良いでしょう。
盆栽の代表的な資格の中でもおすすめの資格を紹介します。
盆栽教室の講師を中心とした活動を考えている人は、日本インストラクター技術協会の「苔玉士資格」がおすすめです。

盆栽・苔玉の種類や手入れ方法と共に、知識や技術を指導できる実力を証明する資格なので、専門的な知識と指導力が求められる講師に適しています。
また、資格内では基礎的な部分の知識も証明できるため、盆栽の基盤販売でもお客様に予備知識を教えながら販売していけます。
以下は協会が開催する資格試験の概要です。
| 受験料 | 10,000円(税込) |
| 受験方法 | 在宅受験 |
| 合格基準 | 70%以上 |
| 申込方法 | 協会の公式サイトの資格ページから |
また、試験日程は以下のようになっています。
| 資格検定試験 | 2ヶ月に1回開催(2,4,6,8,10,12の1年に6回) |
| 申込期間 | 該当月の1ヶ月前の初日から末日まで例:2月の試験の申し込みの場合は、1月1日から末日まで |
| 試験期間 | 該当月の20日から25日の6日間 |
| 答案提出期限 | 該当月の30日必着(2月のみ28日) |
| 合格発表 | 翌々月の10日 |
受験の条件に学歴や特定の講座の受講などは求められていないため、誰でも受験可能な試験です。

2ヶ月に1回のペースで開催されていますが、試験月に受験するには1ヶ月前以内に申し込みを完了する必要があります。
学習が完了する目途が立ったら、早めに申し込むと良いでしょう。
盆栽基盤の販売を中心にした活動を考えている人は、日本デザインプランナー協会の「盆栽士資格」がおすすめです。

盆栽に関する体系的な知識を明らかにできる資格であり、環境に対応した育成や需要に合わせた盆栽への理解が必要な基盤の販売では様々な場面で役立ちます。
また、盆栽教室でも幅広い知識から受講生のレベルに合わせて教えていけるでしょう。
以下は協会が開催する資格試験の概要です。
| 受験料 | 10,000円(税込) |
| 受験方法 | 在宅受験 |
| 合格基準 | 70%以上 |
| 申込方法 | 協会の公式サイトの資格ページから |
また、試験日程は以下のようになっています。
| 資格検定試験 | 2ヶ月に1回開催(2,4,6,8,10,12の1年に6回) |
| 申込期間 | 該当月の1ヶ月前の初日から末日まで例:2月の試験の申し込みの場合は、1月1日から末日まで |
| 試験期間 | 該当月の20日から25日の6日間 |
| 答案提出期限 | 該当月の30日必着(2月のみ28日) |
| 合格発表 | 翌々月の10日 |
盆栽士資格の試験も受験の条件がなく、2ヶ月に1回のペースで開催されています。
在宅受験はネットではなく送付された答案用紙などを封筒で返送する形式なので、提出期限に注意して早めに取り組みましょう。
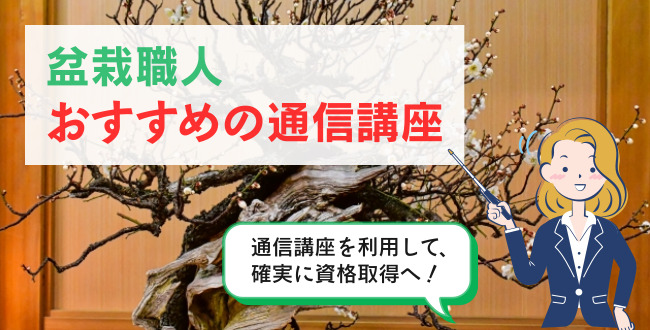
苔玉士資格と盆栽士資格にはそれぞれの協会が認めた2つの通信講座があり、過去の試験を参照した教材で資格試験に向けた学習が可能なおすすめの講座です。
協会認定の2つの通信講座の概要を紹介します。
諒設計アーキテクトラーニングでは「盆栽士W資格取得講座」が、苔玉士資格と盆栽士資格の試験向けた内容になります。
基本講座の概要は以下の通りです。
| 対象となる資格 | 苔玉士 盆栽士 |
| 受講料 | 59,800円 分割:3,300円×20回(初回4,276円) |
| 受講期間 | 6ヶ月(1日30分の勉強想定) 最短2ヶ月 |
| 添削回数 | 5回 |
盆栽職人の監修を受けた教科書で学びながら、5回の添削課題の提出で学習内容を確認していきます。

他にも練習問題や資格試験と同じ形式で受ける模擬試験などが付属しており、両方の資格試験に対応できる知識が身に付けられます。
一方、スペシャル講座の概要は以下の通りです。
| 対象となる資格 | 苔玉士 盆栽士 |
| 受講料 | 79,800円 分割:3,800円×24回(初回3,891円) |
| 受講期間 | 6ヶ月(1日30分の勉強想定) 最短2ヶ月 |
| 添削回数 | 5回+卒業課題1回(資格試験免除) |
教材は基本講座と同じ物を使用しますが、スペシャル講座では協会が発行する卒業課題が付属しています。
卒業課題は5回の添削課題の終了後に取り組めるようになり、卒業課題の提出まで完了すると、2種類の盆栽資格を資格試験免除で同時取得できます。

協会認定の通信講座でしか用意されていない課題であり、本来は2回の受験が必要なところを1回の課題提出で資格が取得できるのは大きなメリットです。
2種類の盆栽関連資格を保有していれば、2つの協会から認められるほどの盆栽に対する知識や理解度の高さを示せるようになります。
受講料が高くなりますが、お金に余裕がある人は卒業課題による同時取得を検討してみましょう。
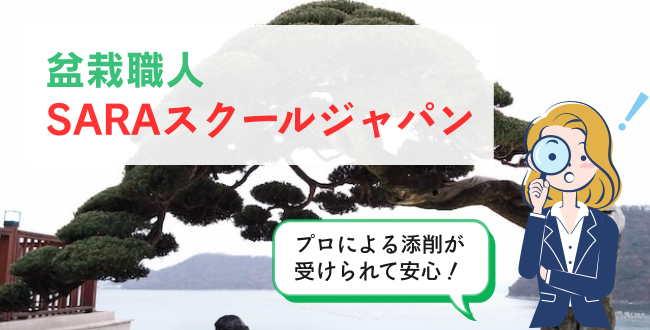
SARAスクールジャパンでは「盆栽・苔玉資格取得講座」が、苔玉士資格と盆栽士資格の試験向けた内容になります。
基本コースの概要は以下の通りです。
| 対象となる資格 | 苔玉士 盆栽士 |
| 受講料 | 59,800円 |
| 受講期間 | 6ヶ月(1日30分の勉強想定) 最短2ヶ月 |
| 添削回数 | 5回 |
教科書や添削課題で学習を進めて、練習問題や模擬試験から試験で出題されるような問題を練習できます。

また、教材に付属した質問用紙やメールを使って専門スタッフへの質問も可能で、受講期間中は何度質問しても無料で対応してくれます。
一方、プラチナコースの概要は以下の通りです。
| 対象となる資格 | 苔玉士 盆栽士 |
| 受講料 | 79,800円 |
| 受講期間 | 6ヶ月(1日30分の勉強想定) 最短2ヶ月 |
| 添削回数 | 5回+卒業課題1回(資格試験免除) |
基本コースの教材で学習を進めて添削課題が終わり次第、卒業課題に取り組めるようになります。
卒業課題の形式は添削課題と同じであり、コース内で学べる範囲から問題が出題されます。
そのため、普段の教材での学習がしっかりできていれば、確実に資格取得できる課題です。
盆栽職人は、主に盆栽基盤の販売や盆栽教室の講師として仕事を行っていき、活動で実績を残していけば、自作の盆栽の販売や展示をしていけるようになります。

盆栽職人を始めたばかりだと思うような売れ行きや盆栽作りができない時もありますが、根気よく活動すれば自分の変化や成長にやりがいを感じながら仕事を続けられます。
盆栽職人としての活動を始めたい人は、2種類の盆栽資格の同時取得が目指せる、協会認定の通信講座の利用がおすすめです。
通信講座の公式サイトでは講座のカリキュラムや無料の資料請求が行えるので、詳しい情報を確認してから資格試験や卒業課題による資格取得を検討してみてください。